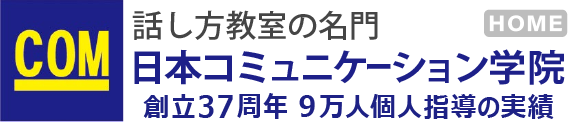「対立しない社内交渉術!他部署と協議するときの伝え方の基本|話し方教室直伝」(じっくり教養 話し方教室東京)
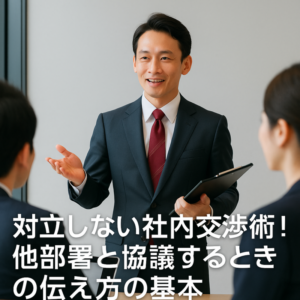
企業の業務は、一つの部署だけで完結することはほとんどありません。営業、企画、製造、開発、情報システム、総務、人事など、各部署が異なる役割を担いながら成果を生み出します。そのため、他部署との協議は日常的に発生します。
しかし実際には、「話がかみ合わない」「相手が全然理解してくれない」「協議の場がギスギスする」といった悩みが多いのも事実です。
その原因は、相手の考え方や評価基準が“自分の部署と違う”ことにあります。同じ会社で働いていても、優先度・責任・判断軸は部署によって異なります。だからこそ、他部署との協議には「ただ伝える」のではなく「関係を保ちつつ合意をつくる話し方」が必要になるのです。
今回は、「対立せずに社内交渉を進めるための伝え方の基本」を整理して紹介します。
1.相手を理解し目的を明確にする
協議は、会議室に入る前から始まっています。準備の質が低いと、どれだけ話し方が上手でも議論は前に進みません。
目的・ゴールを明確にする
「何のための協議なのか」「どこまで決める会なのか」を明確にしておく必要があります。
例えば、「来月のリリースに向けて、仕様Aと仕様Bの優先順位を決定するために相談したい」と、目的を冒頭で伝えることで相手は“協議の枠組み”を理解し、議論が脱線しにくくなります。
相手の立場・制約条件を理解する
一般的に、他部署は意地悪をするつもりはありません。しかし、自部署の責任を守る必要があるのです。
そこで、例えば、相手部署が重視している評価指標、懸念しているリスクや負担、譲れないラインと調整できるライン、こういったことを把握することで、「自分の都合だけの交渉」にならず、協力関係を築きやすくなります。
2.対立を生まない話し方・伝え方をする
協議中に感情的な対立が生まれると、その後の関係にも影響します。そこで重要なのが、相手を尊重しながら自分の意見を伝える話し方です。
まず相手の意見を受け止め、次に自分の意見を伝える
相手を否定してしまうと、議論は一気に防御モードに入ります。まずは相手の意見を受け止める姿勢を示さなければなりません。
その言い回しは、「おっしゃる通り、その観点はとても重要ですね」「その点については理解します。その上でご相談したいのですが…」のように、相手を認めた上で、自分の意見を伝える。この順番が大切です。
要求ではなく“依頼”として伝える
強く主張すると反発を生み、弱く言い過ぎると意図が伝わりません。そこで、ちょうど良いのが「依頼の形」です。
たとえば、「この対応は、必ずお願いします」はお勧めできない話し方です。この場合は「こちらとしては○○が必要なため、△△の形で対応いただけると助かります」の方ががよいでしょう。
相手への敬意を保ったまま、自分の意図や必要条件を明確に示すことで、協調的な関係を保てます。
3.真意を引き出し合意形成、協議記録を残す
協議とは、相手を説得する場ではありません。「一緒に落としどころを見つける場」です。そのためには、相手の真意を引き出し、話を収束させる力が求められます。
相手の本音を質問で引き出す
表面上の反対意見だけに反応すると、議論は平行線になります。
そこで、「今回、特に重視されている点はどこでしょうか?」「懸念されている点は、具体的にどの部分でしょうか?」のように、相手の“不安”や“守りたい条件”が言語化されると、解決策の方向性も見えてきます。
協議を言語化して記録に残す
協議後に「結局どうなった?」となると、時間のロスと不信感につながります。そこで、以下は記録として残します。①決定事項 ②次にやること(担当・期限) ③保留事項 この3点は言語化して残してください。
議事録や共有メモで、これらを確認し、その場で言葉として残すことで、協議は前に進みます。
話し方教室の視点/酒井学院総長の一言
対立しない社内交渉のポイントは、「相手を説得する」のではなく「相手と協力関係を築く」ことにあります。他部署の立場や制約を理解し尊重しながら自分の意図を明確に伝えることで、協議はスムーズに進むものです。
話し方・伝え方が変われば、社内の人間関係も成果も変わります。協議は“勝ち負け”ではなく、“共に組織目標を達成するためのプロセス”であることを忘れないでください。
■ 記事関連・話し方講座/あがり症専門 話し方教室・目的別・話し方講座一覧
■ 話し方教養講座提供/©話し方教室の名門・日本コミュニケーション学院(東京)/話し方教室教養講座・スタッフ委員会