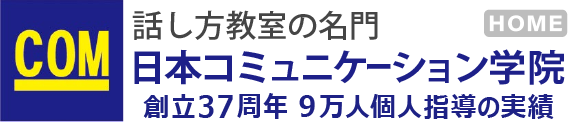「部下への”期待”の伝え方!話し方教室が教える“信頼される話し方”の基本」(じっくり教養 話し方教室東京)

部下に「期待している」と伝えることは、リーダーシップに欠かせない重要なスキルです。しかし、伝え方を誤ると、部下がプレッシャーを感じたり、「結局何を期待されているのか分からない」と戸惑ったりすることがあります。
上司が適切な伝え方をすることは、部下のやる気・主体性・仕事への責任感を引き出す上でとても大切です。今回は、部下への“期待”の伝え方を整理して解説します。
1.期待は具体的な“行動レベル”で伝える
「もっと頑張ってほしい」「しっかりやってくれ」などの抽象的な伝え方は、部下にとって曖昧で判断が難しく、行動に結びつきません。期待は必ず“行動ベース”で伝えることが基本です。
何を、どうして欲しいか具体的に伝える
たとえば、「営業力を高めてほしい」ではなく、「商談の冒頭で結論を先に伝えてみよう」「相手のニーズ整理の質問を増やしてみてほしい」といったように、具体的な行動に落とし込むことで、部下は何をすれば良いか明確に理解できます。
期待を“根拠”を示して伝える
期待を押し付けるのではなく、部下の強みや行動を根拠として伝えると、心理的に受け入れやすくなります。たとえば、「あなたの作成資料はいつも論点が整理されていてわかりやすいから、今度は、大型案件の資料づくりをお願いしたい」というように、承認と期待をセットにすると、部下は前向きになりやすく、信頼関係も深まります。
2.期待を伝える“タイミング”と“場”を考える
期待を伝える際は、タイミングが非常に重要です。忙しい場面や他のメンバーがいる前で急に伝えると、プレッシャーや誤解を生むことがあります。
成功体験の直後に伝える
部下が成果を出した直後は、自己効力感(自分にはできるという感覚)が高まりやすい状態です。このタイミングで期待を伝えると、部下はポジティブに受け止め、次の行動にスムーズに移れます。
たとえば、「この交渉のまとめ方はとても良かった。次は少し難易度は上がるが、〇〇の件でも、その力を発揮してほしい」というように、成果と結びつけた伝え方は効果的です。
1on1での対話形式で伝える
期待を上司が一方的に伝えると、ただの“指示”になってしまうことがあります。
そこで1on1での双方向コミュニケーションにすることが大切です。1on1なら「今回の仕事を通して、どんな力を伸ばしたいと思っている?」「次のステップについてどんな風に考えている?」など、質問を交えた形式にすることができます。そうすることで、部下は安心して主体的に目標を捉えることができます。
心理的安全性が保たれた状態で期待を伝えることが、信頼される話し方の基本です。
3.期待とフィードバックを継続して部下を成長させる
期待は一度伝えれば終わりではありません。むしろ、継続的にコミュニケーションをとり、フィードバックを重ねることで、部下は安心して成長の方向性をつかんでいきます。
プロセスを評価・承認する
結果だけを評価するのではなく、部下が取り組んだプロセスを言語化して承認することが、モチベーションを高める重要なポイントです。
たとえば、「資料の構成を工夫していた点がとても良かった」「ヒアリング内容を丁寧に記録していたのが成果につながった」といった具体的な承認は、部下の行動の再現性を高めます。
改善点は“事実ベース”で伝える
改善が必要な場面では、人格ではなく“行動の事実”に焦点を絞ります。「会議で説明が長くなり、要点が伝わりにくい場面があった。次回はポイントを2つか3つに絞ろう」といったように、具体的でコントロール可能な内容にすることで、部下は前向きに受け入れられます。これにより、期待が“重荷”ではなく“成長機会”として伝わります。
話し方教室の視点/酒井学院総長の一言
部下に“期待”を伝える話し方のポイントは、具体性・タイミング・継続性です。左記を意識して、伝え方を変えるだけで、部下の主体性は大きく変わります。
部下が「自分は期待されている」と実感できれば、より高いパフォーマンスを発揮するようになるのです。そしてそれが、組織全体の成果にも直結します。
■ 記事関連・話し方講座/あがり症専門 話し方教室・目的別・話し方講座一覧
■ 話し方教養講座提供/©話し方教室の名門・日本コミュニケーション学院(東京)/話し方教室教養講座・スタッフ委員会