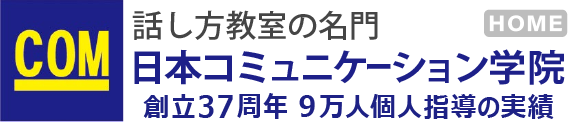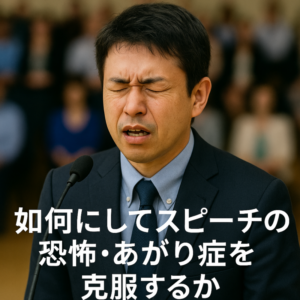「会議がまとまらない原因は?ファシリテーションの基本を話し方教室が伝授」(じっくり教養 話し方教室東京)

会議の一般的問題。「いつも時間だけ過ぎていく」「意見が出ない」「結局何も決まらない」——多くの現場で聞かれるのがこの悩みです。その背景には、実は“参加者の能力”ではなく“ファシリテーション不足”が存在しています。
本学にも、会議運営の相談は多く寄せられています。会議の諸問題に共通する主な要因は、「進行役が議論を正しく扱えていないこと」にあります。
そこで、今回は、会議を活性化し、自然に結論に向かわせるためのファシリテーション術を、リーダー・管理職がすぐに使える形で解説します。
1.発言しやすい“場づくり”が会議を活性化する
心理的安全性を高める
まず押さえるべきは、会議がまとまらない組織ほど「発言しづらい雰囲気」が存在するという事実です。
参加者が自分の意見を出せない環境では、議論は深まらず、結論に至ることも難しくなります。そこでファシリテーターが最初に行うべきは、心理的安全性を高める“場づくり”です。
会議冒頭で表情を柔らかくし、簡単なアイスブレイクで緊張をほぐすだけでも、空気は大きく変わります。また、参加者の発言を否定せず、まずは最後まで聴き、内容を短く要約して返す姿勢を持つことで、「話しても大丈夫だ」という安心感が生まれます。
安心感がある会議では自然と発言量が増え、議論が止まることもなくなります。
具体的な問いで全員を巻き込む
さらに、発言が偏る会議には共通する特徴があります。それは「問いかけが曖昧」という点です。
「何か意見はありませんか?」と抽象的に投げかけても、多くの人は発言できません。そこで有効なのが具体的な問いで参加者を巻き込む方法です。たとえば、「現場の立場から見ると、この案のリスクは何ですか?」「営業部門の視点では、どこにメリットがありますか?」といった具合に、立場や視点を指定した質問をすることで、発言しやすくなり、議論が自然に広がります。
会議を活性化させるための最初のポイントは、この“発言しやすい場づくり”に尽きます。
2.議論を見える化し発散から収束へ向かわせる
論点を可視化し参加者の理解を揃える
会議がまとまらない2つ目の原因は、「議論の論点が整理されていないこと」です。
発言が出ていても、参加者それぞれが別々の論点について話していると、会議は必ず迷走します。そこでファシリテーターに求められるのが、議論を可視化し、構造的に整理する力です。
ホワイトボードや共有画面を使いながら、「事実」「意見」「課題」など区分をつくり、発言を位置づけていくことで、議論の全体像が見えるようになります。
可視化は、参加者の理解を揃えるために非常に効果的な手法であり、会議がまとまらない組織ほどこのプロセスが抜けています。
発散と収束を切り替え会議の生産性を高める
また、優れたファシリテーションでは「発散」と「収束」を明確に切り替えています。アイデアを広げる発散の段階では、とにかく自由に意見を出してもらうことが重要で、否定は厳禁です。
しかし、いつまでも発散だけを続けると、結論に至らず会議が終わってしまいます。そこで収束に移る際には、「今日はこの基準で候補を絞ります」と評価軸を言語化し、優先順位を整理しながら結論に向けて進めます。
この切り替えのタイミングを誤らないことが、会議の生産性を大きく左右します。
3.意見対立を捌きアクションプランで締める
対立処理は視点を整理し共通の目的で統合する
そして、会議がまとまらない最大の原因とも言われるのが、意見の対立を適切に扱えていない点です。
会議が活性化すれば、当然ながら異なる意見が生まれます。しかし対立は“悪いこと”ではなく、“より良い結論に近づくための材料”です。大切なのは、どちらが正しいかの判断ではなく、それぞれの意見の価値を整理する姿勢です。
ファシリテーターは双方の意見を要約し、「A案はスピード優先の視点」「B案はリスク管理の視点」といったように位置づけを明確にします。そのうえで、会議全体の共通目的に立ち返りながら、折り合いを探っていくことで、対立が前向きな議論へと変わります。
“誰が・何を・いつまでに”を決めて会議を終える
最後に、会議を確実に成果につなげるためには、“締め方”が最も重要です。
どれだけ活発な議論ができても、「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかが曖昧なままでは、翌日には忘れられ、行動につながりません。
そこで、会議の終盤にファシリテーターが、決定事項・担当者・期限を一つずつ確認し、全員の認識を揃えることで、会議は初めて実行力のあるものになります。「他に追加や修正はありませんか?」と最後に確認するだけでも、参加者の主体性は大きく変わります。
話し方教室の視点/酒井学院総長の一言
会議がまとまらない原因は、決して参加者の能力不足ではありません。正しいファシリテーションが機能していないだけといってよいのです。
もっとも、ファシリテーターは能力を高めなければなりません。上述したポイントを一つ一つ実践してものにする必要があります。そして、それらを習得できた時、どんな会議も活性化し、組織の成果につながる“生産的な時間”へと変えていけることでしょう。
■ 記事関連・話し方講座/あがり症専門 話し方教室・目的別・話し方講座一覧
■ 話し方教養講座提供/©話し方教室の名門・日本コミュニケーション学院(東京)/話し方教室教養講座・スタッフ委員会