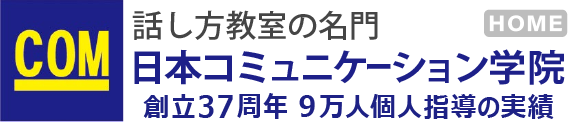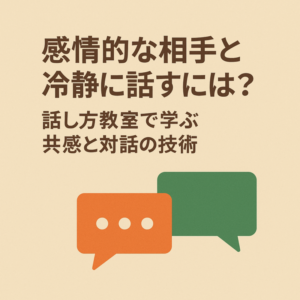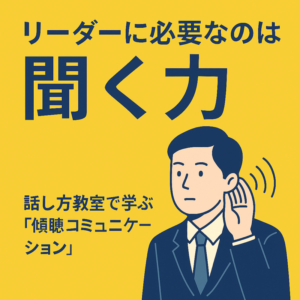「結論が出る会議の進め方:話し方教室で学ぶ!ファシリテーション実践術」(1分間 話し方教室東京)
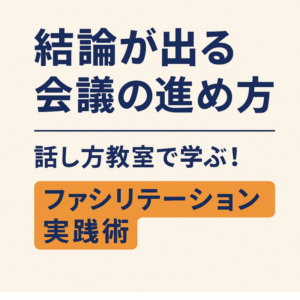
「結局、何も決まらなかった」会議のあとにこんな言葉が漏れる職場、あなたの周囲にもありませんか?
長時間の議論を経ても結論が出ず、ただ疲労感だけが残る――それは、組織全体の非効率を生む深刻な課題です。こうした「結論の出ない会議」を脱却するために、会議の進め方とファシリテーション技術が重要になります。
「話し方」と「進行スキル」は切り離せないもの。準備と進行の段階で正しいアプローチをとることで、結論を導く会議が実現します。今回は、結論を出す会議の設計術をご紹介します。
1. 会議の目的と論点を明確にする
まず会議の目的を明確にする
まず重要なのは、その会議が何を目的としているのかを明確にすることです。意思決定の場なのか、情報共有なのか、あるいはアイデア創出のブレインストーミングなのか。目的によって、話し方も進行方法も変える必要があるのです。
「目的を明言してから会議を始める」ことは基本中の基本です。それによって参加者の集中力や思考の方向性も整います。
次に論点を事前に共有する
結論の出る会議には、論点の事前整理が欠かせません。議題と論点を箇条書きで共有し、当日の時間を「情報収集」ではなく「意思決定」に集中できることが肝心です。
(例)
決定事項:◯◯の導入可否
議論すべき点(論点):導入のコストと効果
意見を求める対象:現場責任者、営業リーダー
このような論点設計を会議前に行っておくことが、議論の迷走を防ぎ、結論への近道となります。
2. ファシリテーションの基本技術
全員の発言を引き出し議論を活性化
ファシリテーターは、単なる進行係ではありません。議論を活性化し、参加者全員の発言を引き出す役割を担っています。
たとえば、「この視点について、別の立場からの意見はありますか?」「現場で感じている課題は、どんなものがありますか?」という具合に、一方通行の会議を避け、対話のキャッチボールを生むことで、より多角的な議論が実現すること、それがファシリテーターの役割なのです。
話が広がったときの論点整理力
話が逸れたときなどは、ファシリテーターが論点を可視化しながら整理するスキルが求められます。
たとえば、「ここまでで出ているのは、A案とB案の2つです。A案の強みは◯◯で、B案は◯◯。この2つを比較して決める方向で進めてよろしいですか」
このように、「論点を言語化し、地図を描くように整理すること」が会議ファシリテーションに欠かせないスキルになります。
3. 結論を出す会議の終わり方
決定事項を言語化して記録に残す
会議の最後に「何が決まったのか」を言葉にして確認することで、参加者全体の納得感と責任感が格段に高まります。
「では、本件についてはA案を採用し、来週中に試験運用を開始するということになりました。よろしいですね?」こうした合意の言語化と確認作業が、実行力のある会議を生み出します。会議は議論するだけでは価値がありません。実行してナンボなのです。
次のアクションや会議予定を明示する
あわせて、「次に何をするか」「いつどこで再確認するか」を明らかにすれば、会議は“機能する場”としての役割を果たせます。
(例)
次回の会議:◯月◯日(火)10:00〜@会議室A
宿題事項:◯◯の調査(担当:◯◯さん)
このように、決定事項と次のステップをセットで提示する締め方が、実務につながる会議を生み出すのです。
話し方教室の視点/酒井学院総長の一言
結論の出る会議を実現したいあなたへ——
「話し方」×「ファシリテーション」は、どんな会議にも応用できる最強の組み合わせです。話し方の技術を身につけ、ファシリテーション力を高めることで、チームも組織も動き出します。
そして「リーダーとは、会議でチームを引っ張り、結果をだす人」そう言ってよいでしょう。どうぞ、リーダーの皆さん、ファシリテーション技術を磨き、会議を機能させてください。
■ 記事関連・話し方講座/話し方教室・目的別・話し方講座一覧
■ 1分間 話し方教室 提供/©話し方教室の名門・日本コミュニケーション学院(東京)/話し方教室コラム・スタッフ委員会/酒井学院総長監修