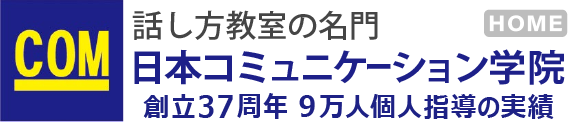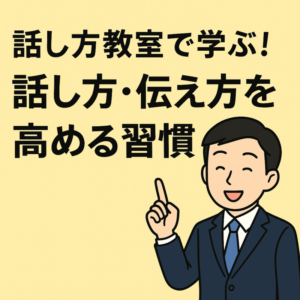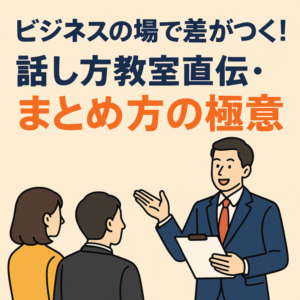「部下が動く!話し方教室が教える“伝わる指示の出し方”の基本」(1分間 話し方教室東京)
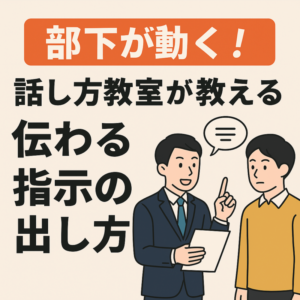
「ちゃんと伝えたはずなのに、部下が思った通りに動いてくれない…」「繰り返し指示しているのに、伝わっていないような気がする…」
こんな悩み、ありませんか?実は、部下が動かないのは、能力ややる気の問題ではなく、**「指示の出し方」**に原因があることも多いのです。
今回は、ビジネスの現場で成果を出すための“伝わる指示の出し方”の基本中の基本を紹介します。
1. 指示の目的を明確に伝える
目的を伝える
人は理由がわからないまま行動を求められると、やる気が出ません。「この作業をお願い」「この資料を作っておいて」と言われても、何のために、が見えなければ、行動の優先順位をつけられないのです。
そこで、「目的→内容→締切」の順で伝えてください。それが基本です。たとえば、「来週の経営会議で新規事業の進捗を報告する必要がある。そのための進捗状況の資料を、今週金曜までに作成してほしい」といった具合です。
このように、冒頭で「なぜ必要か」を説明することで、指示の意味づけができ、部下の納得感や行動力が高まります。
仕事の位置づけを伝える
指示された仕事が、組織やプロジェクト全体のどこに位置づけられているのかを伝えることも大切です。これによって、部下は「自分の仕事がどう貢献しているか」を理解し、主体性を持って取り組めるようになります。
たとえば、「この資料は、我が部門全体の目標達成状況を示すものになるので、目標対比、昨年対比の数字は、必ず入れてほしい」と補足するだけで、目的意識がグッと高まります。
2. 指示は具体的かつシンプルに伝える
抽象的でなく具体的に伝える
「しっかり頼む」「適当にまとめて」などの曖昧な言葉は、受け手にとって判断基準が不明確です。たとえば「早めにやって」ではなく、「今日の17時までに仕上げてください」のように、期限を明示するだけで指示の伝達力は格段に上がります。
仕事の指示では、「曖昧語」を避け、「数字」「具体例」「動詞」で伝える習慣を徹底することが大事です。これは、ビジネスコミュニケーション全般の基本です。
一文一指示を原則とする
一度に複数のことを伝えると、相手は混乱してしまいます。たとえば、「この資料のチェックと修正、それから会議の準備もよろしく」と一気に伝えても、どれから手をつけるべきか迷ってしまいます。
「一文一指示」を心がけることが基本になります。そして、必要ならリスト化して順序をつけます。たとえば、「まずこの資料の全体構成を見直してください。そのあとに数字を更新してください。そして最後に誤字脱字を念のため確認して」というように段階を示すと、部下は迷わず動けます。
3. 指示の復唱を求め進捗確認を怠らない
正しく伝わったどうか確認する
相手が理解したかどうかは、「わかりました」という返事だけで判断してはなりません。指示内容を相手に「復唱してもらう」ことが重要です。
たとえば、「じゃあ、確認の意味で復唱してもらえるかな?」と問いかけ、復唱してもらうことで、伝達ミスや誤解の発生率が大きく減少します。
適宜、進捗確認とフォローを入れる
一度指示を出して終わりではなく、適切なタイミングで「どこまで進んでる?」「何か困ってることある?」と声をかけることで、進捗管理と心理的安全性の両方を確保できます。
特に、若手社員や経験の浅い部下にとっては、この「気にかけてもらっている」感覚が、行動力や責任感につながります。この「声がけフォロー」も忘れないことが肝心です。
話し方教室の視点/酒井学院総長の一言
「部下が動く指示」とは、単なる命令ではなく、“行動を引き出すコミュニケーション”と言えます。あなたが、リーダー、管理職なら、上記のポイントをすぐに実践してください。そうすることで、チームの動きは驚くほどスムーズになるはずです。
あなたの指示の出し方が、部下の成長を引き出し、組織の成果を左右するのです。決して大げさに言っているのではありません。このことを忘れないでほしいと思っています。
■ 記事関連・話し方講座/話し方教室・目的別・話し方講座一覧
■ 1分間 話し方教室 提供/©話し方教室の名門・日本コミュニケーション学院(東京)/話し方教室コラム・スタッフ委員会/酒井学院総長監修